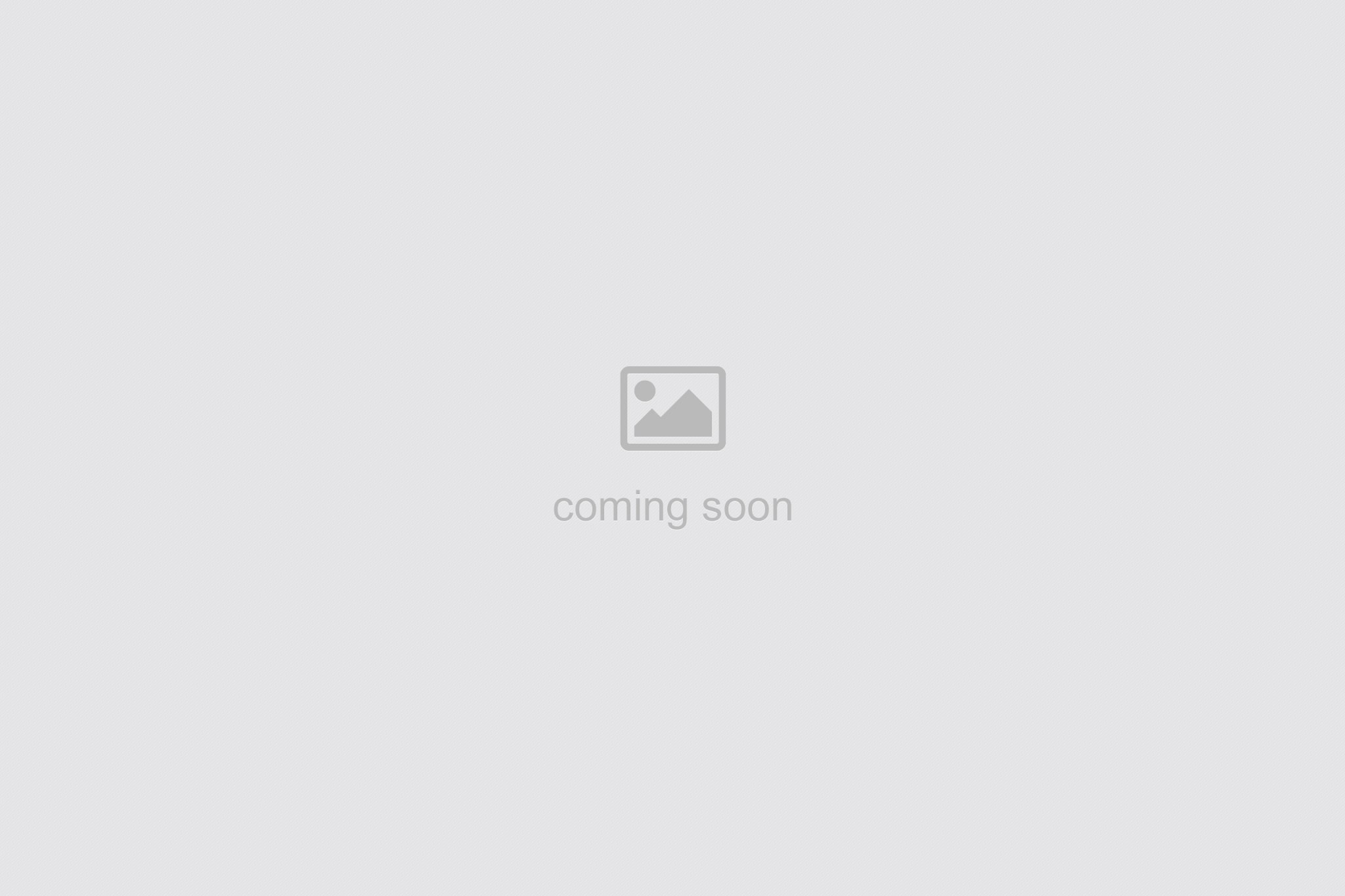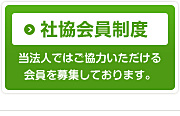計算書類、現況報告書は、WAM NETの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページで公表されています。
令和4年度 事業報告
令和4年度 事業報告 (2023-11-07 ・ 4924KB) |
令和3年度 事業報告
令和3年度 事業報告 (2022-11-09 ・ 4678KB) |
令和2年度 事業報告
令和2年度 事業報告 (2021-10-11 ・ 5914KB) |
令和元年度 事業報告
令和元年度事業報告
令和元年度事業報告 (5382KB) |
自立支援部門
日向市生活相談・支援センター心から(生活困窮者自立支援制度)
出前講座(※東郷域のみ実施)
相談事業 (※東郷域のみ実施)
日常生活自立支援事業(あんしんサポートセンター)
①福祉サービスの利用援助
❀福祉サービスの利用、または利用をやめるために必要な手続き、福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
❀住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び行政手続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な支援
❀福祉サービスの利用料を支払う手続き
②日常的金銭管理サービス
❀年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
❀医療費を支払う手続き
❀税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
❀日用品等の代金を支払う手続き
❀上記に記載する手続きの支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預入の手続き
③書類等の預かりサービス
❀年金証書、預貯金通帳、権利、契約書類、保険証書、実印・銀行印
❀その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)
法人後見体制整備事業
生活福祉資金貸付事業
(1)貸付対象世帯について
①低所得者世帯
資金の援助及び指導を受ける事により自立できると認められる世帯
②障害者世帯
身体・知的・精神障がい者世帯で手帳の交付を受けている者が属する世帯
③高齢者世帯
65歳以上の高齢者が属する世帯
上記に記載する世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的として設けられた貸付制度です。
(2)資金の種類
①総合支援資金
失業等や、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費の貸付
②福祉資金
生業費用や技能習得等に必要な経費。緊急的措置には緊急小口資金で対応
③教育支援資金
高等学校、大学、専門学校等の入学に必要な経費及び就学資金
④不動産担保型生活資金(要保護)
居住用不動産を担保に高齢者世帯への生活費貸付
(3)償還指導の支援
宮崎県社会福祉協議会の担当職員と連携して、月に1~2回、借入滞納者宅を訪問して現在の状況等を把握することに努めています。また、本会では払込票の送付事務を行い、民生委員と協力して償還指導を行います。訪問によって、滞納状況が把握でき、償還計画等の相談に応じています。
(4)事業効果と今後の課題
本事業の利用を相談される世帯は、金融機関やその他の公的制度が利用できない低所得者世帯であり、家族や親族等からの生活支援も望めない場合も少なくありません。そのため、自立に向けた貸付を行っても、償還時に計画的な返済が出来ないことも少なくありません。本会では多少のリスクを見込んでも、償還指導を通して対象世帯と継続的な関わりを持つことによる自立に向けた支援の実現に重点を置いています。特に教育支援資金については、子どもの育成や将来への夢や希望の実現のために、長期的な支援を前提として、民生委員等の関係機関と連携しながら生活支援を行っています。
たすけあい資金貸付事業 ※法人単独事業
[貸付限度額] | 5万円 |
[返済方法] | 無利子 返済期間最長10ヶ月 |
[貸付条件] | 連帯保証人(6月以上日向市在住で保証能力のある方) 申込者の居住地担当民生委員からの意見調書提出 |
事業効果と今後の課題
借入相談を受けた場合は、相談者世帯の状況をきちんと把握し、その世帯が抱える課題を明確にしていきます。その上で、本資金の貸付がこの世帯の自立援助に繋がるものであるかを精査しています。
高齢者自立支援マネジメント(介護保険サービス事業)
地域支援部門
小地域福祉活動推進事業(地域福祉コーディネーター配置)

(1)「住民が身近な圏域」において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決することができる環境の整備 (2)「住民が身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備 |
◇地域調査・診断、実態把握、地域座談会(地域アセスメント) ◇地域課題抽出・報告及び地域福祉情報発信(地域カルテ) ◇課題解決のための“支援”及び関係機関への連絡調整 ◇地域生活支援会議の開催 ◇住民主体による小地域福祉活動の実施及びその支援 ◇地域福祉推進基礎組織構築(地域組織化) ※自治会での地域福祉部を設置するための支援・協力 ◇小地域福祉推進会議開催(福祉部への支援・協力) ◇福祉教育・人財育成事業の企画・推進、人財の組織化・活用 ◇地域福祉活動計画作成支援(6包括圏域) ◇多機関・多職種による地域福祉活動実践 |
日向市福祉推進員事業 (※東郷域のみ実施)

日向市東郷町福祉推進協議会(地域生活支援会議)

日向市東郷町福祉推進協議会(地域生活支援会議)

事業実践では専門職・地域住民を含めた多様な主体による生活支援サービス提供体制の構築に向け、人材育成や地域資源の掘り起こし・運用、既存組織とも連携構築を図りながら取り組みました。
認知症地域支援体制構築等推進事業

ボランティア・市民活動支援センター

日向市民生委員児童委員活動の推進
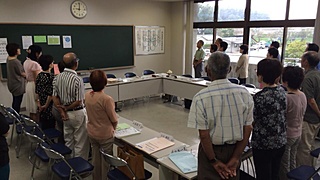
日向市社会福祉施設等連絡会

福祉教育の推進

日向市地域福祉コーディネーター連絡会(通称:おせっ会)

区 分 | 大王谷 | 財光寺 | 中 央 | 日知屋 | 南 部 | 東 郷 | 市 外 | 合 計 |
おせっ会 | 5名 | 11名 | 8名 | 8名 | 3名 | 5名 | - | 40名 |
がむしゃら応援団 | 16名 | 22名 | 22名 | 11名 | 9名 | 13名 | 12名 | 105名 |
合 計 | 21名 | 33名 | 30名 | 19名 | 12名 | 18名 | 12名 | 145名 |
在宅支援部門
介護保険サービス
障がい福祉サービス
その他の介護サービス(市受託)
家族介護者支援(在宅介護者の会「思いやりの会」)
法人運営部門
日向市駅東駐車場管理運営事業

日向市老人福祉センター管理運営事業

児童館・児童センター管理運営事業
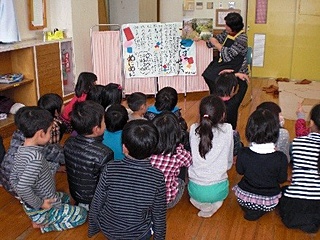
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

レクリエーション機材貸出事業